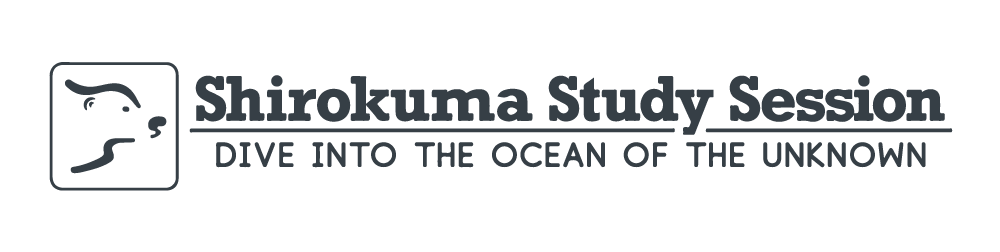こんにちは!しろくまスタディセッションのコヤマケイコです🐻❄️✨
自分の学習法が本当に成果につながっているかどうか、冷静にチェックすることが大切です。たとえば、「今のやり方で成績は本当に上がっている?」など、自分に問いかけてみましょう。もし素直に「はい」と言えないなら、学習法を見直すタイミングかもしれません。
なぜ成果が出ていないのに、同じ学習法を続けてしまうのか!?👀
多くの人が、今のやり方でなかなか成果が出ていないと感じていても、「変えることでうまくいかなかったらどうしよう」という不安や、「これまでの努力を無駄にしたくない」という気持ちから、つい同じ学習法を続けてしまうんです。
たとえば、模試のスコアが伸び悩んでいるのに、単語帳や過去問のやり方を変えず、「あと少しで受かる気がする」と思い込んでしまう…そんな経験、ありませんか?これは「今のままで大丈夫」と自分に言い聞かせてしまう、心のクセなんですよね。現状維持の安心感は、一時的には心地よいものです。でも、そのまま同じやり方を続けてしまうと、時間や労力を無駄にしてしまうリスクが高まります。
間違った方法を修正できないままでは、毎年同じ失敗を繰り返してしまう可能性も…💀特に「やっている感」や「頑張っている満足感」が強い人ほど、効果の検証や方法の見直しが後回しになりがちです💀💦
特に毎日何時間も勉強しているのに成果が出ない場合、「やっている感」に満足してしまっていることが多いです。たとえば、精読に時間をかけすぎて全体の読解力が伸びなかったり、ディクテーションで細部にこだわりすぎて大意をつかむ力が育たなかったり…。
※精読について:辞書で調べて構造を解析して、その文は丁寧に読めるようになるけど、スピードや全体把握力が育たない。
※ディクテーションについて:「1語も逃さず正確に書く」ことに集中することで、全体像よりも細部にこだわるクセがついてしまう。「会話のおおよその流れ」を取る力が鍛えられない。
大切なのは、「その努力が本当に弱点に効いているか?」を常に検証し、「あるべき努力の姿」に持っていくことなんです。その第一歩は、自分が何のためにやっているのかを明確にすることです!以下のような問いかけを自分にしてみてください🎵
・今の学習法は、試験で点を取るための訓練なのか?
・それとも、自分の知的好奇心を満たす楽しみなのか?
・どちらも大事なら、時間配分は明確に分けられているか?
学習法を変えることは、決して「今までの努力を否定する」ことではありません。むしろ、「新しい可能性を広げる」ための前向きな一歩です。成果が出ていないやり方に固執せず、合格者のやり方や自分の弱点に合わせて柔軟に方法を変えていく勇気が、未来の成功につながります✨