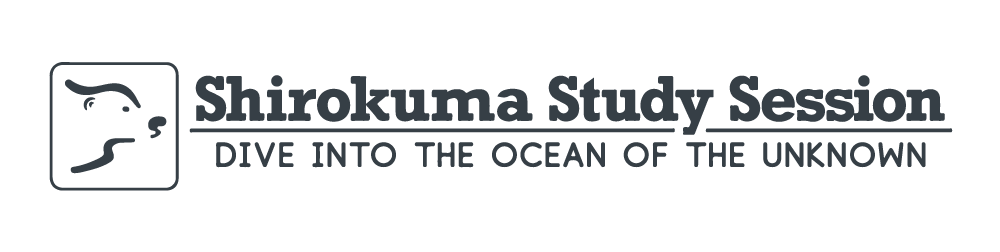コンテンツ利用時のルール
当事業では、サイトの利用者の方の学習密度・学習効率の向上のため、学習材料となるコンテンツを自由にご利用いただきたいと思っています。当サイトのコンテンツをご自身のブログやSNSでご活用いただいたとしても、都度連絡していただく必要はありません。しかしながら、様々なトラブルを防ぐために、コンテンツをご利用いただく際に、守っていただきたい著作権に関する法律があります。参考と引用のルールです。
参考と引用の違い
どちらも出典元を明らかにするという共通点がありますが、異なる部分もあります。かんたんにまとめると「自分の言葉にするか・しないか」という点で大きく異なります。
参考とは
出典元のコンテンツを参考にして書く時は、「自分の言葉」に書き直す必要があります。
引用とは
出典元のコンテンツを引用して書く時は、「一切改変せず」、引用部分だけでコンテンツが終わらないようにする必要があります。
参考にも引用にも必要な大原則
- 出典元を明記する。
-
「しろくまスタディセッション」(Shirokuma Study Session)や「コヤマ ケイコ」などの名前、もしくは各種SNSアカウント名を書くだけでいいです。可能であれば、該当するページのURLがあると嬉しいです。
-
SNSアカウント名 - @shirokuma_study_session
- @ShStSession
出典元を明記していただかないと、コンテンツの「パクり・パクられ」騒動に発展しかねません。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、ご協力よろしくお願いいたします。
参考にする時のルール
- ■絶対に守ってほしいこと
- 出典元を明記する。
- 「しろくまスタディセッションのサイトを参考にしました」「参考:しろくまスタディセッション」などでOKです。
- 同じ内容を書くとしても、自分の言葉に書き直す。
- コピー&ペーストをする場合は、引用のルールを使う必要があります。少し言葉を変えるだけでいいので、自分の言葉で書き直してください。
引用する時のルール
- ■絶対に守ってほしいこと
- 出典元を明記する。
- 「引用元:しろくまスタディセッション」などでOKです。
- 引用部分をひと目で分かるようにする。
- 「以下、しろくまスタディセッションのサイトからの引用です」と書いたり、ブログなどであれば背景を変えたりして、パッと見で引用開始と終了の箇所がどこだか分かるようにします。
- 引用するときは、文字や絵などは改変せず、一語一句同じものを使う。
- 表現を少しでも変更すると、それは「参考」したことになります。当サイトから「引用した」とは書かないようにしてください。
- コンテンツの量のバランスを自分発信の部分>引用部分を心がける。(9:1程度が目安)
- 引用だけでご自身のコンテンツが終わらないよう気をつけてください。きっちり9:1にしなくて構いません。自分発信のコンテンツが、引用部分よりも多ければOKです。
- 引用する必要性や文脈を説明する。
- なぜ引用するのか、を説明しましょう。「重要だと思ったから」「学習に役立つと思ったから」などのような言葉です。
不安・心配な時/商用利用の時
個人で利用される場合に、参考なのか引用なのか、よく分からない、というときは「とにかく出典元を明記する」というルールだけお守りいただければ大丈夫です
企業として提供されているサービス等で引用・参考にされる場合は、CONTACTより1度ご連絡いただけますと幸いです。
このページは、下記2つのウェブサイトを参考にして作成しました。
・「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」/ TOPCOURT
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote
・「引用・参考・参照・転載の違いと使い分け。書き方のルールを例とともに紹介!」/ ferret
https://ferret-plus.com/8057
2020/12/27 最終更新