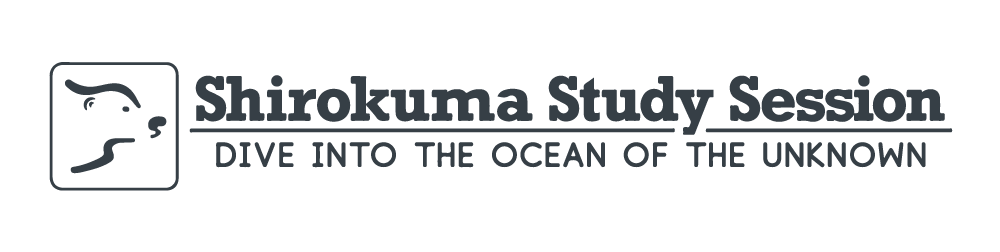こんにちは!しろくまスタディセッションのコヤマケイコです🐻❄️✨
リーディングとリスニングの学習tipsの連載もついに、Part 7まで来ました🎵
今日はリスニングやスピーキング対策中の方が練習で陥りやすい現象について説明します!
試験勉強をしていると、過去問に取り組み、自己採点をした結果、「やっぱりダメだな…無理かも…」と、心のなかで後ろ向きな発言を連発してしまうことがあるかと思います。
そして時にはそのフラストレーションをインスタグラムで明るく振る舞いながらも投稿したり、友人やAIチャットボットに打ち明けたりしているでしょうか。
こうした「素直な感情の吐き出し」は、気持ちをリセットするための大切なプロセスです。
感情を吐き出すことで、一時的に気持ちが軽くなり、また机に向かう力が湧いてくれば、その「吐き出しプロセス」はうまく作用しています✨
たとえば、「今回はここがだめだったけど、次はこのようにしてみよう」などと前向きに対策を考え、気持ちを次へ切り替えられる場合は、気持ちのリセットがうまくいっている証拠です。
しかし、感情の吐き出しが「自己批判の反すう(繰り返し)」になってしまうと、思考や気持ちが「停滞した状態」に陥ってしまっているかもしれません。
・リーディングやリスニングの正解率が悪くて、「自分はダメだ」「頭が悪い」「合格は無理なんだろう」といった否定的な言葉が頭の中で繰り返される
・スピーキング対策で言葉が詰まった後、10分以上引きずる
・ライティングで指摘されると自信をすべて失い、フィードバックが受け入れられなくなる
・SNSや人前では明るくふるまっていても、内心では「劣等感ループ」に陥っている
・失敗や不足を何度も思い返し、気持ちが重くなる
・「うまくできないのは、バカだから、◯◯【資格や経験】を持ってないから」と、論理が飛躍した理由付けをする
このような状態では、フラストレーションが蓄積するため、同じミスを繰り返してしまい、本質的な改善の機会を失うといった悪循環に陥りやすくなります💀
この悪循環から抜け出すために大切なのは、「感情のあとに、分析」をセットにすることです。
・ミスや失敗を「自分についての新たな発見」と捉え、「失敗=知識の穴が見えたチャンス」と考える
・「私は~ができない」という自分主体の批判的な表現ではなく、「この問題に取り組むときは、◯◯が不足していた」と具体的に課題を言語化する
このように、感情を出すのはOKですが、そのあとに必ず「原因→対応」を考える習慣を持つことが、本質的な改善につながります✨✨
こちらは、真面目で真剣に取り組んでいる方ほど陥りやすい現象です!ぜひ振り返ってみてください🎵