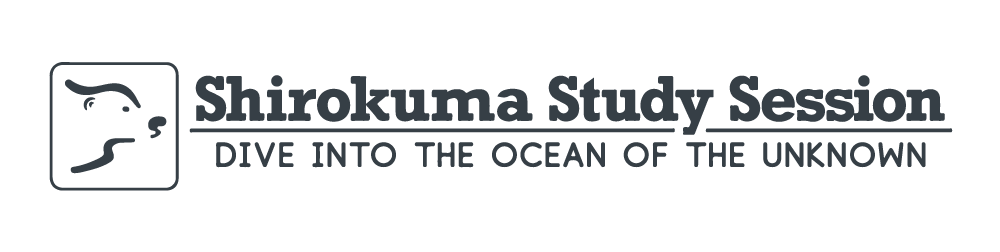中高生のお子さんが「英語は人生に必要ない」とか「英語は捨てる」とつぶやいたことはありませんか?
単語テストの不合格が続いたり、長文が読めなかったり、英検の作文で白紙になってしまったり。そんな経験が重なると、「自分には向いていない」という思い込みが強くなっていきます。その結果、自分から復習をしなくなったり、テスト前でも「どうせ無理」と投げ出してしまったりする様子が見られるかもしれません。
英語の特徴は、基礎の上に新しい知識を積み重ねていく点にあります。例えば、現在完了を学ぶには過去分詞の理解が必要で、関係代名詞を理解するには基本的な文の構造を知っている必要があります。つまり、基礎がしっかりしていないと、新しい単元に入るたびに「わからない」という経験が増えていってしまうんです。(数学もそうですよね。わたしはそれで数学を早い段階で諦めました😂)
学校の英語の授業では、カリキュラムの都合上、決められたペースで次々と新しい単元に進んでいかなければなりません。そのため、基礎が十分に定着していない生徒さんも、否応なく新しい内容に進まざるを得ない状況が生まれています。
例えば、be動詞がまだ曖昧なまま三人称単数のsを学び、現在形が完全に理解できていない段階で過去形に進み、さらには関係代名詞や仮定法まで…というように、「わからない」が積み重なっていってしまうんです。
先生は個々の生徒さんの理解度に合わせた指導をしたいところですが、限られた授業時間や一般的な先生の過密スケジュールの中では難しく、お子さんの理解度に合わせた指導が難しいと思います。(特に私立だと、学校の方針として、成績優秀者に目がいきがちで💀)
多くの場合、お子さんは「自分がどこでつまずいているのか」を明確に説明できません。「今さら be動詞がわからないなんて言えない…」と思って、黙ってしまうこともあります。そして授業はどんどん進み、テストは応用問題が増え、「何をすればいいのかわからない」という状態に陥ってしまいます。
結果として、試験での赤点を回避するためだけの「表面的な理解」や「暗記だけの学習」になってしまいがちです。とりあえず試験範囲の表現を試験直前に丸暗記しようとするけど、それは長期記憶に繋がりません。そのため、努力のわりに、長期的な成果にはならないのです。だから次の試験でも引き続きゼロからのスタートとなってしまい、苦労をするんですよね。
そのため、大切なのは、「テスト範囲の復習」だけでなく、「つまずいている基礎」に立ち返る機会を作ることです。例えば、現在完了のテストの点数が悪かった場合、現在完了だけを復習するのではなく、「過去分詞は理解できているかな?」「基本的な文の組み立て方は大丈夫?」といった、もっと基本的な部分を確認してみる必要があります。
中学3年生だったら、中1と中2の範囲をおさらいする必要があるかもしれません。
そして高校3年生だったら、中1から高2までの範囲をおさらいする必要があるかもしれません。
学年が進めば進むほど、復習は大変になります。1度でも赤点に近い数字を定期試験でとったら、なるべく早い段階で、「その範囲よりも前の範囲」を復習できるよう、環境を整えていきましょう。
とはいえ、「英語はいらない」と思っている子どもに、復習のための教材を渡しても、おそらく取り組まないでしょう。これはわざとやらないのではなく、これまでの「失敗経験の積み重ね」があまりにも多すぎて、英語に対し無気力になってしまっているからです。
だから、「うちの子はいつまでたっても英語を勉強しないから赤点ばかり」「赤点ばっかり取るのを、どうにかしようと努力しない」「怠慢だ」などと責めないでくださいね。